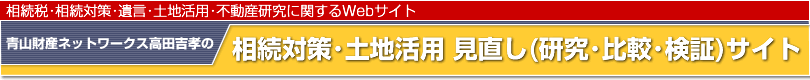
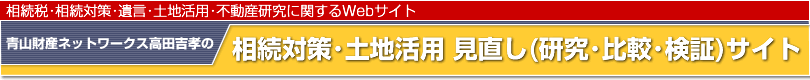
相続税対策の原則は、出来るだけ早く、また多くの対策を組み合わせて行うことですが、事後であっても節税対策の余地はあり、また相続発生後の対策・実行も重要です。
相続発生後の相続税の軽減ポイントは、土地の評価と遺産分割の工夫にあります。遺産分割にあたっては、今回の相続税の軽減だけを考えるのではなく、相続税の有利な納税方法、相続人の所得税の軽減及び次の相続税の軽減を考慮した遺産分割が必要になってきます。
この他にも株式を相続する場合の工夫などもありますが、ここでは上記の2つのポイントに絞って簡単に解説します。
小規模宅地の特例の利用
土地の分割取得で評価を下げる
土地の面積は、1面積の土地(利用の単位となっている1区画の土地をいいます)ごとに評価します。なお、相続、遺贈又は贈与により取得した土地については、原則としてその取得した土地ごとに評価します。すなわち、相続人の相続発生時の状態で評価するのではなく、相続後の取得者ごとに、かつ、利用単位ごとに評価します。
このように、土地の評価は利用単位ごとに行うのが原則ですが、例えば、空閑地を相続人で分割して取得し相続人ごとに異なる利用であれば、不合理な分割でない限り、遺産分割後の利用単位に応じ評価することができます。したがって、相続が発生した後でも、路線価の異なる2つの道路に面した土地は、工夫して分割することによって評価額を引き下げることができます。
(1)のような路線価の異なる2つの道路に面した土地400m2が相続財産にあるとします。この土地を1人で相続した場合の相続評価額は、図の計算のように4億600万円になります。この土地を(2)のように2つに分割して、それぞれの土地を別の相続人が取得するようにします。この場合の相続税評価額は図の計算のように2億2500万円となり、分割して取得することによって評価額が半分近くに下がることが分かります。
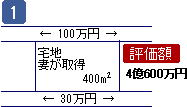 |
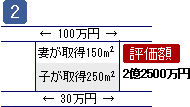 |
| (100万円+30万円×0.05)×400m2=4億600万円 ・普通商業・併用住宅地区では二法路線影響加算率は0.5 ・奥行き価格補正率は無視する |
(1)1100万円×150m2=1億5000万円 (2) 30万円×250m2=7500万円 (3) 合計(1)+(2)=2億2500万円 |
★不合理分割は認められないので注意する
ただし、分割した土地の両方について宅地として利用できるだけの面積が必要です。遺産分割によって著しく不合理な土地の分割が行われた場合には、分割前の土地を一各画地として評価してから、各相続人に面積をもとにその評価額を按分することにないります。例えば(3)のような分割は、不合理分割となり認められません。
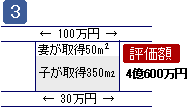
相続または遺贈により財産を取得した者が被相続人の配偶者であるときは、一定の要件のもとにその配偶者の相続税額が軽減されます。そこで、今回(第一次相続)の納付すべき相続税をもっとも少なくするためには、配偶者が相続する額を、法定相続分又は16,000万円以下にすればよいことになります。
しかし、第一次相続に続いてその配偶者の相続(第二次相続)が同時に連続して発生した場合や、又は発生しそうな場合には、配偶者が第一次相続においていくら遺産を相続すれば有利 かの判定は、第一次相続及び第二次相続の相続税を通算して判定する必要があります。
連続して同年中に相続が発生した説例1(生存配偶者に固有の財産がない)の場合では、同年中に相続が発生し相次相続控除を考慮すると、配偶者が80%相続することが第一次・第二次相続における通産相続税額はもっとも少なくなります。しかし、第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間が1年を超えるときは、相続者が遺産の30%ほどを相続するのが最も有利になります。
なお、これらの相続税は被相続人の遺産の額・法定相続人の数及び構成により異なります。
1. 被相続人 父(平成16年2月死亡)
2. 父の遺産 10億円
3. 相続人 配偶者+子2人
4. 配偶者固有の財産はないものとする
| 相続割合 | 第一次相続の税額 | 第二次相続の割合 | 合計税額 | |||
| 配偶者:子 | 配偶者(1) | 子(2) | 1年以内 相続発生(3) |
1年超2年以内 に相続発生(4) |
1年以内に 相続発生 (1)+(2)+(3) |
1年超2年以内に相続発生 (1)+(2)+(4) |
| 10:0 | 166,500 | 0 | 121,250 | 137,900 | 287,750 | 304,000 |
| 9:1 | 133,200 | 33,300 | 121,200 | 134,520 | 287,700 | 301,020 |
| 8:2 | 99,900 | 66,600 | 121,150 | 131,140 | 287,650 | 297,640 |
| 7:3 | 66,600 | 99,900 | 124,760 | 131,420 | 291,260 | 297,920 |
| 6:4 | 33,300 | 133,200 | 131,830 | 134,710 | 297,880 | 301,210 |
| 5:5 | 166,500 | 138,000 | 138,000 | 304,500 | 304,500 | |
| 4:6 | 199,800 | 98,000 | 98,000 | 297,800 | 297,800 | |
| 3:7 | 233,100 | 58,000 | 58,000 | 291,100 | 291,100 | |
| 2:8 | 266,400 | 25,000 | 25,000 | 291,400 | 291,400 | |
| 19 | 299,700 | 3,500 | 3,500 | 303,200 | 303,200 | |
| 0:10 | 333,000 | 0 | 0 | 333,000 | 333,000 | |
※ 留意事項:設置例3までにおいて同じです。
1. 税額は平成16年度の税率により計算されています。
2. 子は均等に相続するものとして計算しています。
3. 税額控除等は配偶者の税額軽減及び相次相続控除額のみとして計算しています。
(10億円−16,650)−7,000万円=76,350万円(第二次相続時の遺産額)
(76,350万円×1/2×50%−4,700万円)×2人=28,755万円(第二次相続の税額)
28,775万円−16,650万円(相次相続控除額)=12,125万円
| 1 | 各相続人等が取得した課税相続財産価格 | − | その人が負担 した葬式費用・債務の額 | + | 相続人から3 年以内に贈与された財産の価格 | = | 各相続人等の課税価格 |
| 2 | 課税価格の合計額 | − | 遺産にかかわる基礎控除=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) | = | 課税遺産総額 |
| 3 | 課税遺産総額 | × | 各相続人の法定相続分 | × | 税率 | − | 速算表の控除額 | = | ||
| 各相続人の法定相続分による相続税額 | ||||||||||
| 4 | 各相続人の法定相続分による相続税の合計額 | = | 相続税の総額 |
−参考文献−