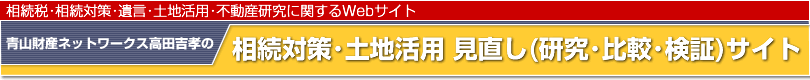
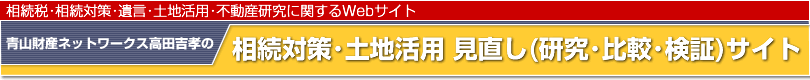
日本の資産家の平均的財産構成をみると、不動産(土地と家屋)が約70%(近年は低下傾向)を占めています。多くの資産が不動産(土地と家屋)で占めていることから、不動産管理会社の活用による相続対策が有効であり、また不可欠です。
この対策は、被相続人に集中する不動産収入の分散による毎年の所得税対策と、その収入が被相続人に累積することを防止することにより長期的に見て大きな効果をあげることを目的としています。
所得税の節税は、オーナーの不動産収入から不動産管理会社に管理料を支払い、かつ、管理会社の役員をオーナーの家族にし、その役員に給与を支払うことにより、不動産管理会社を通じて、オーナーの不動産収入をオーナーの家族に、合法的に分散を図ることにより超過累進税率の適用を低く抑えることになり節税に役立ちます。
相続対策としては、原則として不動産管理会社の出資は、オーナー自身やその配偶者が出資することを避け、子供たちによる株主構成とします。そして、不動産管理会社にオーナーの所有する高収益な不動産を売買などの方法により移転を図れば、より多く家族役員などへ給与の支払いが可能となり、相続人への金融資産の移転が実現し、相続税の納税資金の準備に役立てることができます。
以下に、不動産管理会社の設立目的から設立判断のポイントなどを説明します。なお、本文中「不動産管理会社」と表記している場合は、同族会社である不動産管理会社のことを言います。同族会社でない(一般的意味合いの)管理会社のことをいう場合は、単に「管理会社」又は「市中の管理会社」と表記しています。
収益物件から生じる所得は、物件の所有者に帰属します。したがって、個人所有の物件の場合には、収入が個人に集中し、高所得となってしまいます。また、所得税・住民税の税率は超過累進税率構造になっているため、高所得になるほど負担すべき税金も重くなってしまいます。
そこで、不動産管理会社を通じて所得を分散させれば、各人の所得金額を押し下げることができ、その結果税率区分の引き下げを図ることができます。このことは次の所得税・住民税の簡易税率表と図を見ていただければよく分かると思います。
つまり所得を分散させることにより、一人あたりの所得金額を減少させることができ、その税率区分も低い部分が適用できるため、家全体の所得税・住民税の負担が軽減される訳です。
| 税 目 | 所得税 | 住民税 | 合算 | ||
| 所得金額 | 税率 | 控除額 | 税率 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0 | 一律10% | 15% | 0 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 | 20% | 97,500円 | |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 | 30% | 427,500円 | |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 | 33% | 636,000円 | |
| 900万円超〜1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | 43% | 1,536,000円 | |
| 1800万円超 | 40% | 2,796,000円 | 50% | 2,796,000円 | |
※ 実際の税額は、この他に人的控除の差に対応した減額措置が講じられます。
個人オーナーに入るべき所得の一部を会社へ分散化させることによりオーナーの金融資産の増加を防止し相続財産の膨張を防ぎます。つまり、オーナーに係る相続税の負担を軽減できます。
会社に所得を移転させたら、その所得を給与という形で分配します。給与については、その受給者に対して所得税等が課されますが、給与所得には給与所得税控除(概算経費)があるため、課税対象が小さくなります。このとき、給与の支給先を個人オーナーではなくその相続人とすれば、将来の相続税の納税資金準備にも役立ちます。また、オーナーの所得よりも相続人の所得が少ないことが予測されるため、所得税・住民税の適用税率も低くなり、結果として家全体としてみた場合の税負担が減少します。
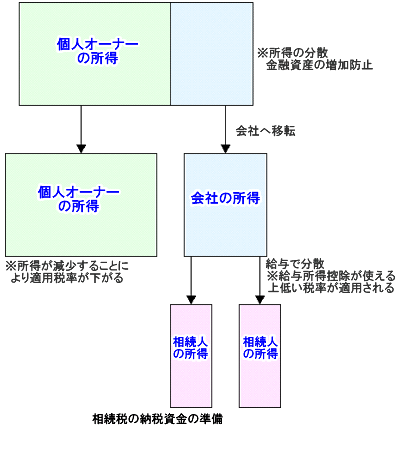
不動産所有者は、あくまでも個人オーナーであり、不動産管理会社は個人の所有物件の管理をいいます。そのため、会社が得るのは「管理料収入」のみとなります。
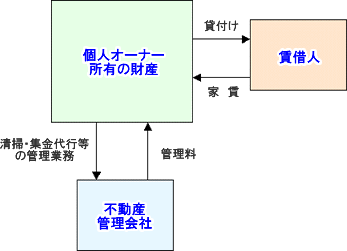
サブリース方式ともよばれる方法で、個人オーナーが所有物件を不動産管理会社に一括で貸し付けます。会社は個人オーナーに借上げ家賃を支払い、一方で借り上げた物件について入居者を募集し家賃収入を得ます。
会社が空室等の経営上のリスクを負うことになりますので、満室時の実質管理料「賃借人−個人オーナーへの支払い家賃」は管理料徴収方式の場合よりも高く設定されるのが一般的です。
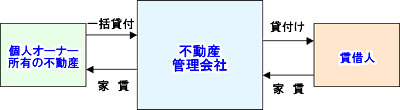
不動産管理会社が物件を取得し、管理運営を行います。会社が建物そのものを所有しますので、家賃収入は100%会社に入ります。個人の家賃収入がすべて会社に置き換えられ、個人としては地代収入が残るだけですので、収入の分散効果はこの不動産所有方式が最も大きいといえます。
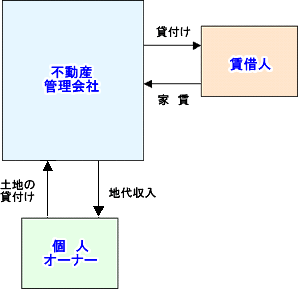
1. 会社設立費用がかかる
2. 個人所得と法人所得とに区分して計算する必要があり所得計算が面倒である。
3. 法人の場合には赤字であっても最低限の税負担(地方税の均等割)が生じる。
4. 法人税の申告等に係る税理士等への費用が必要となる。
5. 社会保険の手続きが必要となる。
※ 不動産管理会社に移転できる所得が少額な場合には、コストが節税メリットを上回り、節税スキームが十分に機能しない場合があります。
本来、法人は営利を目的として活動を行い、その利益を株主に分配することを使命とします。ここでの不動産管理会社の設立の主目的は、重税によって個人の財産が減少していくことを防ぐことであり、その意味で利益追求主義の一般法人とは多少事情が異なります。
不動産管理会社については、その個人の財産希望等によって、その会社をどのように活用していくかを方向付けていく必要があり、それが設立後の会社の運営面に大きく影響してきます。不動産管理会社のあり方としては、それぞれの事情にもよりますが、大きく分けて次の2通りに集約されると思われます。
財産規模が大きい個人になるほど、相続を経るたびに多額の相続税が課せられ、財産を売却したり物納するなどして個人の財産が失われていくのが一般的です。
ところが、個人には相続がありますが、会社には相続という概念がありません。したがって、いったん個人の財産を会社に移転させると相続を経ることなく財産を永続して守っていくことができるのです。もちろん、個人オーナーが会社に対して出資していれば、その所有している法人株式を通じて相続税が課せられることになりますが、株式であれば生前に計画的に次世代に移転させていくことが可能ですし、不動産そのものを移転させるよりも手続きが簡便です。
その一方で個人の財産を会社に移転させる際に資産を所有していたことによる含み益が実現し、それに対して譲渡税が課税されるという問題点をクリアしていくことが大きな課題となります。
相続税はかかりそうだが個人の財産が大きく減少するほどではなく、手持ちの金融資産で充分納税ができそうな方にとって、会社は不動産の所有を目的とするのではなく、収入の分散のためにだけ活用する方法が考えられます。
この場合、会社は所得を通過させることが主目的となりますので、会社が得た収入から必要経費を差し引いた残額はすべて親族に給与を支払って分散させ、会社の所得をできだけ抑えて法人税の負担を軽減させる方法が有効です。
不動産管理会社を設立した場合には、所得の分散による所得税・住民税の節税、金融資産の蓄積防止、相続税納税資金の準備ができるなどのメリットがある一方、会社設立に伴い各種のコストが発生するなどのデメリットがあります。このコストを上回る効果がなければ、不動産管理会社設立の意味がなくなってしまいます。ここでまずポイントになるのは、どれだけの所得を会社に移転できるのかという点です。
個人所得が多いと、所得税や住民税の適用税率も高くなります。したがって所得規模が大きい個人オーナーほど、収入の分散に伴う節税効果はより大きくなります。
納税資金の蓄積という観点から見た場合、親の金融資産を子に移転させる方法としては、金銭を贈与する方法と不動産管理会社を通じて給与の支給を受ける方法があります。
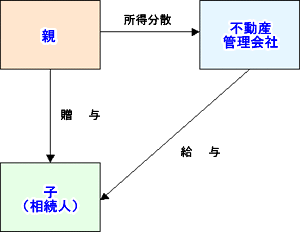
| 項 目 | 主なチェックポイント |
| 株 主 | 父母が株主になっていませんか? |
| 役員報酬の支給 | 父母が多額の役員報酬を受け取っていませんか? |
| 管理料 | 業務の内容に照らし適正な管理料となっていますか? |
| 地 代 | 地代の設定が適正ですか? 土地の無償返還に関する届出書を提出していますか? |
| 不動産所有方式の検討 | 父名義で高収益の建物はありませんか? |
| 父に相続が発生した場合 | 相続税の取得費加算を利用して、不動産管理会社に譲渡できる資産はありませんか? |
| 契約書の作成 | 管理契約書や土地賃借契約書を作成していますか? |
| 債権放棄・増資 | 父が不動産管理会社に対して多額の貸付けをしていませんか? |
「不動産管理会社の活用と税務」 山本和義編著/清文社発行